Side Rizel
終焉の都市
それにしても分からない事が多すぎる。記憶が混乱しているのか、何かが欠落しているのか。何が嘘で何が現実なのか、その全てを見通せなくなっている。
都市エクリスに続く暗闇に沈みながら、ぼんやりと自覚する。心に考える隙はあっても、体は鉛のように重くなるばかりだった。
うた 《辿られた記憶1》
俺は父サーディン・エクリスのように優秀な魔術師ではない。
魔術を扱うにも向き不向きがあり、俺は確実に後者だと自覚している。 どれだけ大きな魔力が潜在していようと、編み上げる知識と覚悟がなければ意味は無に等しいのだ。 だから俺は魔術師になるつもりも、魔術に対する興味すらもない。
それなのに、いつの頃からだったか。目を閉じて眠りに入ろうとすると、とある少女の歌が魔力となって聞こえてくるようになった。 彼女は金色の髪と金色の瞳、そして白い衣装に身を飾り、いつも無邪気に微笑んでいた。
心を奪われたら最後、恐らく全ては「終わる」のだろう。幼いながら本能的にそれを知っていた俺は、耳を塞ぐ事で自分を守った。

始めは耳に僅かに触れる程度の微音。しかし彼女の声は次第に大きくなる。 とうとう無視もできなくなり、俺は夜中に頻繁に目を覚ました。
少女に対してはある種の親しみを覚えていた為、恐怖を感じた訳ではない。ただ睡眠を邪魔されるのは我慢ならなかった。
エルシアと名乗った少女は飽きもせず、同じ声で同じ物語を奏で続けた。俺がどこに居ようと必ず耳元まで追い詰める。
歌声は覚醒の朝まで途切れる事なく続く。お陰で俺は、それらの歌をすっかり覚えてしまった。
自分がおかしくなったのではない、狂っているのはあの少女のほうだ。
そう訴えても家族は幼い俺を奇異な目でしか見ない。あの呪いが聞こえているのはこの耳だけなのだと理解し、俺は口をつぐむしかなかった。
そんな中、母だけは俺を理解し、匿ってくれた。
ある雪の夜、母に連れ出されたのは村から離れた東の森。呪いを絶ってくれる魔術師の屋敷が湖の畔にあるという。
魔術師の名はサーディン。俺はまだこの時、その男が自分の父親であるなどとは知らなかった。
数刻ほど歩いた後、寒さに震えて吐き出した白い息の向こうに水辺が見えた。 雪が降っているのにも関わらず、湖面には満月が映っている。 水面が揺れる度に光は形を崩す。 湖面の月に気を取られている内に母の姿は消えていた。代わりに、ただ一輪の朱い花が残された。
嘘は吐いていない。真実かどうかも問題ではない。
重要なのは、間違いなくこれが俺の「リゼル・アマランス」の記憶だという事実だ。
こうして俺は未来の自分を否定しながら、過去の自分をも騙し続けることになる。
瞳 《辿られた記憶2》
森の奥地、俗に「月映り」や「瞳」と呼ばれる湖の底に、都市への門があった。何一つ生を持たない空間へ繋がる場所である。実際、湖は都市を隠すために映し出された幻だった。都市エクリスは魔力の中でのみ姿を現す呪われた都市なのだ。
そんな湖に俺は体ごと引きずり込まれ、気が付くと白い壁で囲われた部屋に佇んでいた。
周囲は全てが曖昧で、ぼやけた世界だった。こんな状況で自分が正気を保っている事実に失望しながら、注意を四方に滑らせる。
耳に圧力がかかる静寂の中、重く濃い魔力が地を這うのを感じた。害がなくとも気味の悪い力だ。思わず後ずさった時、背中が冷たく堅い何かに触れた。
振り返ると俺の腰の高さほどの壇があった。形状からして祭壇として使われていたものだろう。薄靄に浮き上がる白い壇上には幾重もの装飾が施されている。
霞んでしまってよく見えないが、最も大きく刻まれているのは「エクリス」を意味する紋だった。幾つかの創世の女神の意思の内、最も死と近い力である。あらゆる繋がりを解き放つ意思として、エクリスは現実にも存在していた。
「リゼル・レオゼット・エクリス」
少女の声が俺の名を呼んだ瞬間、冷気は瞬く間に拭い去られた。凍り付きつつあった手足を熱が包み込む。やがて血が通う感覚と呼応するように視界が晴れた。
目映い光に支配され、空中に姿を現したのはエルシア。俺をここへ呼んだのは、エクリスの守護者である彼女以外に考えられない。
「不機嫌ですね、レオゼット」
「……僕は絶望的な金鎚なんですよ。機嫌を気にするなら、湖の底なんかに入り口を造らないで欲しかったですね」
少女の物言いに腹が立ち、わざと毒づく。
「門をそこにしたのはあなたですよ」
どういう意味なのか知らないが、金色の少女は朗らかに笑っている。どんなに造形が整っていても、中身がなければ物と同じだ。変化のない笑み方は蝋人形じみている。
だから俺にとってはこれ以上なく空虚な表情に思えたが、彼女自身は大真面目なのだろう。
「もう歌わないでください。君のお陰でこっちは気が狂いそうだ」
俺の燻る感情など構わない様子で、金色の長い髪を羽のように舞わせながら、エルシアはこちらに接近してきた。
「それはできません。あなたに悪い夢を見せないためですから」
伸ばされた細い指が耳元に触れてくる。髪を梳かれているのに一切の感触がないとはどういう事か。僅かな温度差もなく、彼女は俺とまるで同質だ。気を抜くと自分の意識がエルシアに溶けてしまいそうだった。
「エクリスはあらゆるものを壊します。形も、心も、繋がりも。それをあなたに見せたくないと望んだのは、サーちゃんですよ」
「サーちゃん……?」
俺の復唱に、エルシアは小さく頷いた。
「サーちゃんは優しい人なんです。いつもエルシアが欲しいものをくれました。今も、この地に花を咲かせるために」
何の因果か、エルシアは人としての俺の死を願い続ける忌まわしき亡霊だ。その肉体は遠い昔に死んでおり、この都市に遺されているのは意識だけなのだと、父が言っていた。この都市は彼女の意思を守る為の器でもあると。
誰がこんな残酷な絡繰りを据えたのか、想像するまでもない。俺が生まれる遙か以前から、彼女の金色の瞳はあらゆるものが壊れていく様を視てきたという。
「ねえ、レオゼット。あなたはエルシアと同じです」
俺に呼びかけながらも、俺の返答など求めてはいない。彼女には誰の声も届かないのだ。
「あなたもきっと、永遠を……未知の未来を望みます」
だから俺は何も答えない。代わりに蔑みの感情だけを視線に託してやった。
永遠《辿られた記憶3》
エルシアが、俺の目の前にある小さな木の箱を指した。
「これを知っていますね」
その形には確かに覚えがあった。父であるサーディン・エクリスが造った
それはあの男が息子の為にと作った多くの絡繰りの内、唯一好きになれた箱だった。魔術師である父が俺に与えた玩具は、どれも普通の子どもが扱える類のものではない。魔力や知識を伴わせなければ遊ぶ事すらできないものばかりだ。娯楽の本すらも一般的には解読されていない魔術言語で記されていた。
俺がこの箱を気に入った理由はただ一つ。魔力を使わずとも、自分の指先だけで音を鳴らす事ができたからだ。
「開かれなければ永遠の筈でした。歌う力を残したまま夢を見続ける事ができました。けれど、この箱は……」
エルシアの指が触れるまでもなく、箱は少女の視線のみを受けて自ら蓋を開いた。ここはエルシアの意思が全てを支配する空間である。今更驚く必要はない。
金属製の番が軋む音と共に聞き慣れた金音が旋律をなした。俺とエルシアが留まる空間に馴染んでいく。
優しく懐かしい調べが緩やかに二度繰り返された後、エルシアは再び語り出した。
「捻子を巻き戻すことはできません。一度目覚めてしまった世界は、歌と引き替えに永遠を失いました」
鳴り止まない自鳴琴の前に口を閉ざす少女。よく見れば箱はうっすらと霞んでおり、向こう側にあるエルシアの白い服を透き通らせている。
俺はようやく疑い出した。これは自分自身の記憶に過ぎないのではないかと。何しろ、あの箱はとっくに失くしてしまっているのだ。
一体どこで失くしたのか、肝心な部分は記憶に靄がかかっている。
とにかくこの自鳴琴は偽物だ。この鮮明に奏でられる曲も、俺の記憶が聴かせている幻に過ぎないのだ。
「……君があんなに謳い続けた永遠も、この世界には存在しないって事ですか」
俺の問いかけに否定も肯定もせず、エルシアは動こうとしなかった。
俯きながら両眼に灯された金色の光は、俺ではなく古ぼけた木の箱を直向きに見つめている。
「どうして黙るんですか、エクリスの守護者様?」
彼女の瞳が哀しげな色を宿していると思えたのは初めてだった。狂気で満たされた金色は、涙のないまま泣いていたのかもしれない。そこにある筈の哀しみをただ感じていないだけ、もしくは、真実を現実に映す術を失ってしまっただけなのではないか。
いや、だとしたら何だ。意思も力も魔性そのものの癖に、今になって普通の少女を気取ろうというのか。
「エルシアは何度もあなたの夢を見ました。レオゼットはエクリスの後継者。だからエルシアに永遠をくれるんです。間違うことはありません」
「そんな夢、どうせ間違いだらけですよ」
数百年前に滅んだ都市は存在し、同じく死んだ人間は生き続け、枯れたはずの花は咲き誇る。時は止まり、夢が現実になる。この都市に本当の事など何もない。
「だって君の都市は嘘ばかりなんだから」
虚勢を張ってみたものの、エルシアの拙い一言一言を研ぎ澄まされた呪詛のように感じていた。何気なく発されたものであっても、彼女の言葉には逃れられない力がある。
時間の感覚が麻痺する程に間を置いた後、エルシアはゆっくりと唱えた。
「大丈夫ですよ。あなたはいずれ真実を思い出しますから」
エルシアを振り切りたい危機感とは裏腹に、両の手がじっとりと汗ばんだ。いつもより速く脈打つ鼓動が俺の心を強く揺さぶっている。乾いた唇を噛んで憂鬱に耐えなければ、直ぐさま彼女に取り込まれてしまいそうだ。
「つまり、君が本当に欲しいものは未来じゃないんですね」
息苦しさの中で俺は何とか自分を保ち、奮い立たせる努力をした。
エルシアに同情してはならない。それは後悔を意味するのだ。惑わされるな。この女は全てを知った上で人間をも壊してきた最悪の守護者なのだから。
「君が永遠と呼んでいるのは……」
そして彼女が望んでいるのは、彼女が知り得ない世界そのものなのだろう。
つまり、この都市の終焉である。
花《辿られた記憶4》
一輪だけ咲いていたのは、鮮烈な蒼さを持つ花だった。
魔力を吸収して人に幻影を見せる魔の花リプアラは天空諸島セレスターラにしか咲かない筈だ。
だが、ここが「どこ」なのかは思い出せなかった。記憶なのか、未来なのか、或いはただの幻影なのかすら。
ともあれ、本当の俺は夢を見ているに違いない。ここに至る直前の記憶が真っ暗闇な以上、それだけは簡単に予測がつく。
リプアラが生地セレスターラで咲く姿は美しかったが、ここエクリスでは毒々しい色に見えた。
(――美しい花ほど、咲く場所を間違えてはならないんだよ)
そう言ったサーディンの真意を、俺は一度として知ろうとしなかった。本当に美しい花ならばどこに咲いても美しい筈だと頑なに信じていたのだ。
第一、理解は共有だと思った。同意とはあの男を認める事に等しいのだと、そんな偏った考え方をしていた。
今となっては恥ずべき事だが、俺は自己を確立させる為に、父の全てを否定してきたのだ。それ以上の意味などない。
俺は足下に咲いていたリプアラの茎を手折った。鮮やかな蒼色は確かに空のように透き通っている。
「どうして摘んでしまったの? お花はまだ生きているのに」
花を手にした俺を非難したのは、やはりソフィアだった。 人のやること為すことにけちをつけてくる、うるさいお姫様だ。
「哀れな花だわ。自分に興味もないリゼル・アマランスの気まぐれで、突然命を奪われてしまうなんて」
「人聞きが悪いですよ。痛みを感じる訳じゃないし、どうせ意識も感情もないんだから」
ソフィアに反論した瞬間、俺の中の何かが動いた。ずっと外れていた記憶の欠片が一瞬だけ繋がったような、不思議な感覚だった。
「……花は哀れじゃないと思う……」
遙か昔、誰かに対して、俺は同じことを言ったのだ。
花に心はない、だから哀れではない。そう、胸が張り裂けるほどの確信を持って。
千切られた花が俺の手の中で枯れた。黒く変色した花片は螺旋を描きながら散っていった。
乾ききった花片の行方を目で追いながら、俺は自分に強く言い聞かせる。
「……本当に哀れなのは、君だ、ソフィア」
ここは現実ではないのだから、何も偽る必要はない。
咲くべき場所を違えれば人だって簡単に褪せてしまう。だから終わらせてやった。俺の弱さとソフィアの強さは、俺と彼女を簡単に死へと導いた。
ソフィアが俺を殺したから、俺もソフィアを殺したのだ。
景色が歪む。
エクリスの祭壇で生前の姿のまま凍り付いたソフィアを前にして、俺は言葉もなかった。
彼女が絡む記憶の全てが疎ましい。開かれる事のない蒼色の瞳も、囁かれる事のない甘い声色も、ただ無性に憎いだけだった。
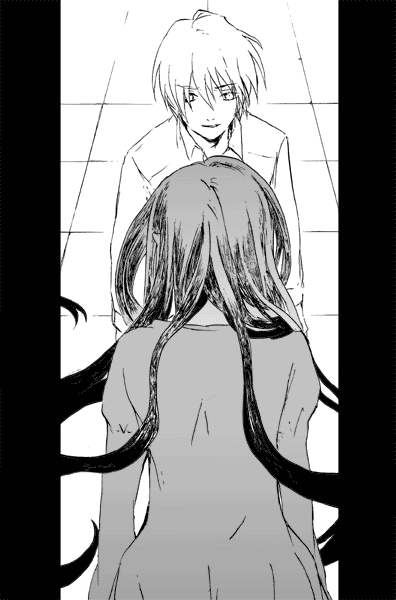
俺は今、以前は拒絶したエクリスの継承を望んでいる。
償いでもなければ、罪から逃れる為でもない。俺は自分が辿るべき未来を知ってしまっただけだ。未来はどんな例外もなく、最初から定められている。自鳴琴の絡繰りが戻りながら決められた音を奏でるのと同じように、ただ在るだけなのだ。
本当に簡単な有限。世界は誰の期待をも裏切る程に単純で明快で機械的だ。
俺の本質はエクリス、エルシアと重なる存在。だからエルシアと同じようにエクリスの守護者になり、結果としてエルシアの願いを叶える。たったそれだけの義務を果たし、同時に俺の中に組み込まれている未来を遂行する。
運命という言葉にもたらされる悲劇的な意味合いは好きではないが、つまりはそういう事なのだ。
だが、ソフィアには判って貰えなかった。彼女は俺を「助けたい」と断言した。これには絶望せざるを得なかった。ソフィアはあの花のように、俺を哀れだとでも言いたかったのだろうか。
そもそも、同じ本質を持たない人間が理解する必要はない。
真実は形にした瞬間に少なからずの変質を来たす。だから俺の本質は俺の中にしかない。すなわち真実とは自分の内側で知るしかなく、例え知ったからといって他人に伝えられる類のものではないのだ。主体に根差す理は自身にしか通じないのだから。
それなのにソフィアは俺を理解しようとした。結果、彼女は死に至った。
「だから、壊れないものは一つで良かったんです」
突然沸いたエルシアの声で、俺は我に返った。
浮かんでいた筈のソフィアの姿は消え、いつの間にかエルシアが同じ場所で微笑んでいる。
疑問を感じるまでもない。この都市はあらゆる死の記憶を内包しているのだ。だから父は、ここを「死の都市」と呼ぶ。
僅かに、俺は頷いた。
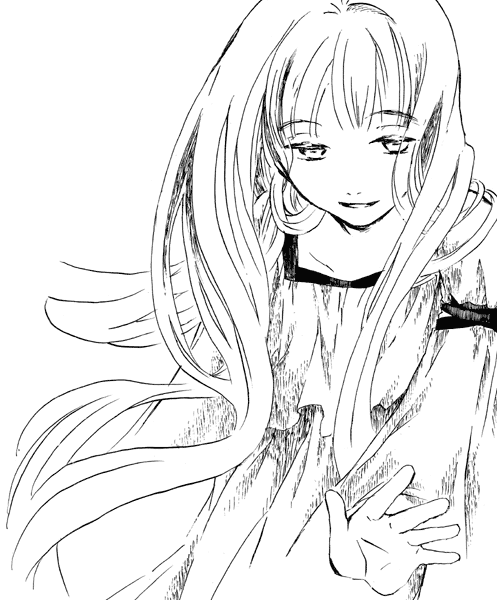
未来《辿られる記憶1》
ここに辿り着くまで、俺の意識は繰り返すだろう。
「あなたが全ての真実を辿ったら、もう一度会いましょうね、『リゼル』」
そう言ったエルシアが俺の唇に右手を翳すと、全身の隅々にまで更に強い圧覚を感じた。呻きたくとも、唇を震わせる事もできない。当然、喉から声が出る筈もなく、俺を造るほぼ全てが停止しているといっても過言ではなかった。もう引き返せないと感じた。
だからこれは予知、未来の記憶である。
間もなく俺は、自分が呼吸すらしていない事に気付くのだ。事実に失望した時、自覚する嗟嘆こそが自己を認識できる唯一の手段だと知る。すると今度は現実を手放す努力をし始めるだろう。心の底から死を渇望し、自由を許された思考だけが支配する肉体から解放されたいと願う。この意識を一秒でも早く引き裂いて欲しいと。
狂いかけた俺に、エルシアはこう言うだろう。
「これは、エルシア・ラグ・エクリスが、エクリスの意思として執り行う、エクリスとあなたとの、守護の契約です」
彼女の言葉は聖典の一節のように、俺に最期の救いを与える。その時、俺は初めてエルシアに神の姿を見るのだ。 混濁した世界から救ってくれる、最愛の女神の意思を。
Side Rizel 了